 50代英語
50代英語 50代からの英語(指示)
指示を確認して下さい。Please check the directions. 分かりました。終わりました。Okay...I'm done 確認し終わりましたか?Are you done with checking? いいえ。もう少し時間を...
 50代英語
50代英語  50代英語
50代英語  50代英語
50代英語  50代英語
50代英語  50代英語
50代英語  50代英語
50代英語  50代英語
50代英語 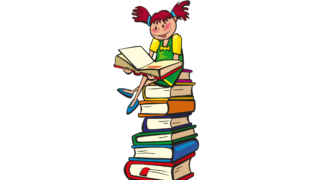 その他
その他 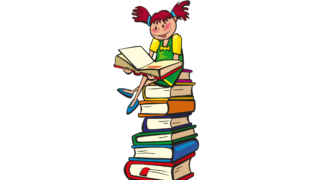 その他
その他  その他
その他